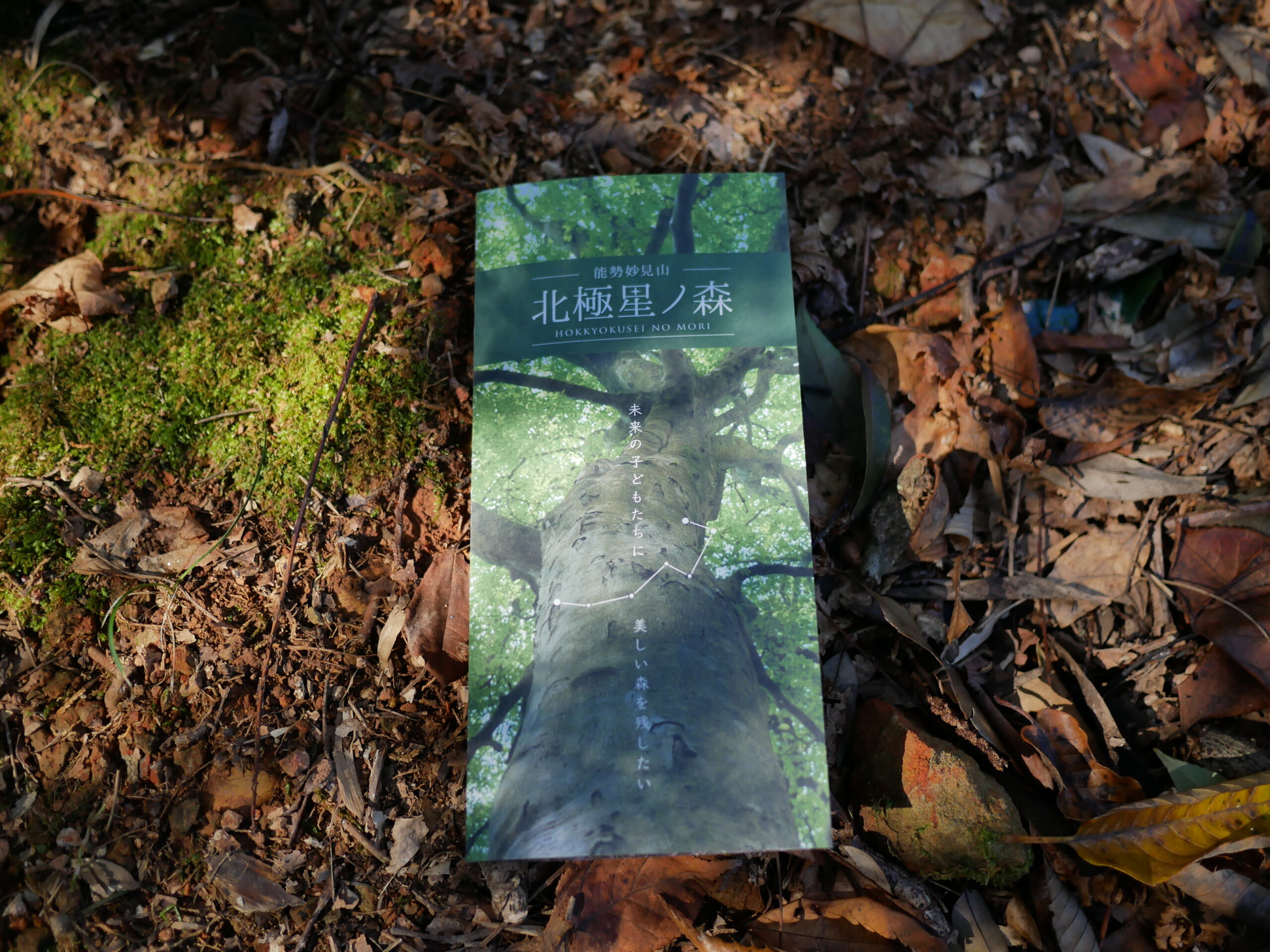九州大学や神戸大学の先生がたを案内して参りました!

神戸大学と九州大学で共同研究をされているご縁もあり、みなさまそろって妙見山のブナ林に遊びに来て下さいましたので、ブナ守の会を代表して事務局がご案内いたしました。興味深い知見がたくさんあったので、ブログに書いておこうと思います。
さて、九州大学宮崎演習林(椎葉村)のブナの話を伺うと、鹿の被害は妙見山よりもひどいようで、林床の草木はシキミなど一部の樹種を除いてシカに食べられているのですが、それだけではなく、糞の調査から、なんと「落ち葉」まで食べていることがわかってきたそうです。
そうなると林床の落ち葉すらほとんどなく、雨と風に削られていくのを座して待つのみといった、ほんとうに極限状態であることが想像されます。
とはいえ、妙見山も余談を許さない状況には変わりなく、今まで食べなかったアセビも新芽については食べられていたり、最近ではシキミの枝を折るようになってきたので、シキミまで食べ出す日も近いかもしれません。そのうち、こちらのシカも落ち葉を食べ出す可能性もあります。
今回、ご一緒させて頂いて、改めて林床に注目しながら妙見山を歩いたのですが、いろいろ発見がありましたので、記録しておきます。
興味深いのは、ホウノキなど葉が大きい木の下は(シカの少ない通常の森では全く問題ないのですが)雨粒が葉の上で大きな塊となって裸地化した林床に落ちることが多いためか、大きくなった雨粒が土を穿ち、細かい根が露出しやすいようです。根が露出してしまうと本体も弱って枯死しやすくなるとのこと。

今が一番落ち葉が多い時期なので大きな違いはよく分かりませんでしたが、来年の夏場にしっかりチェックしてみようと思います。

また、今まで林床は、草は生えていなくてもリター(落ち葉や枯れ枝など)がたくさんあった(気がしていた)のですが、斜面を中心に完全に裸地化しているところも増えてきたので、雨粒対策についても今後は検討していかねばならないかもしれません。
あと面白いのが、地面の露出は苔の状態を見ると分かりやすいとの知見。苔だけが周りの地面から浮いている場合は、その周りが浸食されている場合が多いようです。今まで気づきませんでしたが、確かに!

やっぱり先生方と森を歩くといろいろ発見が多いです。わざわざ紙面に残すほどでもない些細なことこそ「口伝」でしか伝わらないのでかえって貴重です。
参考に今回来られた九州大学の先生がたの研究内容です。
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/993/
余談ですが、今回この寒い時期なのにミヤマクワガタが歩いていました。何らかの理由があり冬眠し損ねたのでしょうか?
この時期のクワガタは初めて見たので衝撃でした。

2025年11月3日