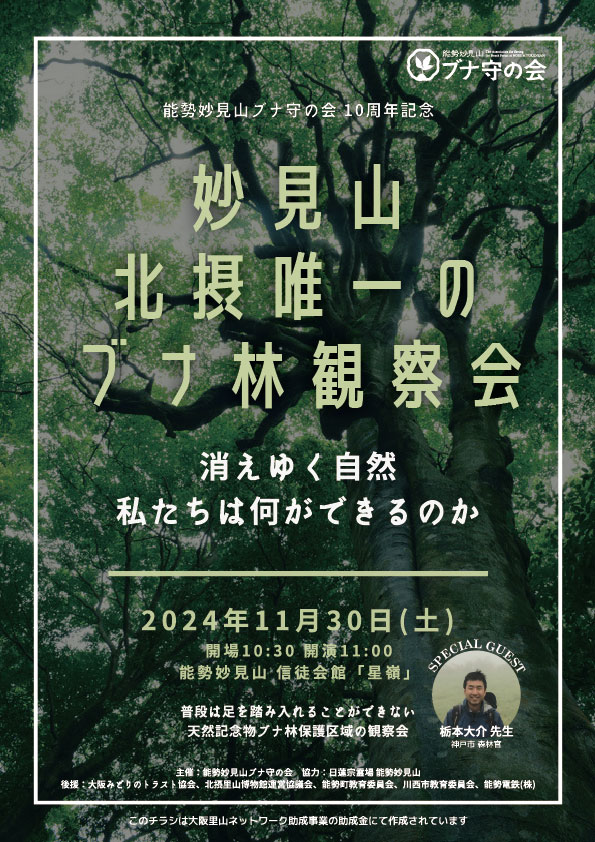5月24日に北摂里山大学のみなさまがブナ林に学習にお越しになりました。
この日はあいにくの雨だったので、基本的なブナ林についての座学は能勢妙見山の絵馬堂をお借りして行いました。

北摂里山大学 学長の服部先生から妙見山のブナ林の特徴について簡単に説明があり、その後、当会副会長より詳細説明をさせて頂きました。
その後、雨の中ではありますが、カッパなどで身なりを整え、いよいよブナ林に行くところですが、ちょっとその前に、ブナの生長の遅さが分かる苗を見学。2年生と3年生のブナを確認します。



引き続き、川西市の天然記念物のパネルを見ながら説明があり、いよいよブナ林に向かいます。

ブナ林は幻想的な霧に包まれており、雨の日にしか見ることのできない樹幹流がブナの幹を伝って流れておりました。
樹幹流は特にブナが多く、他の木でもたまに見ることはできるのですが、幹の外側に水がおちていることが多いです。ブナはどれも自分の幹側に水を流すように枝葉がでているようで、大量の水が幹を伝って地面に注いでおりました。
本日も新しい実生を2本も発見しました!
北摂では滅多に見ることができないブナの実生に、学生の皆様も興味深げにご覧になっておいででした。

日本一のウラジロノキや今が最盛期のヤブデマリの綺麗な花を見ながら、大きなアカガシのある広場へ向かいます。
妙見山で最も大きな幹回りを誇るアカガシは、その根も変わっていて、板のように地面からせり出しています。これを板根(ばんこん)といいますが、地面の岩盤が固すぎて下に根を張れず、上に突き出してきたものだと言われています。
また、面白いことに、岩盤が固いと思われる尾根沿いには水が少なくても大丈夫なアカガシが群生しており、地面が柔らかそうな場所には水をたっぷり必要とするブナ林が広がっています。植生をみることで、地面の下がどうなっているのか想像するのも楽しいですね。

雨の中ではありましたが、雨の日にしか見ることができないブナ林を満喫して頂けたのではないでしょうか。
学生の皆様には北摂里山大学で学んだ知識を自然保護に生かして頂ければと思いますし、そのフィールドの選択肢にぜひブナ守の会もいれて頂けるとうれしいです。
2025年5月28日